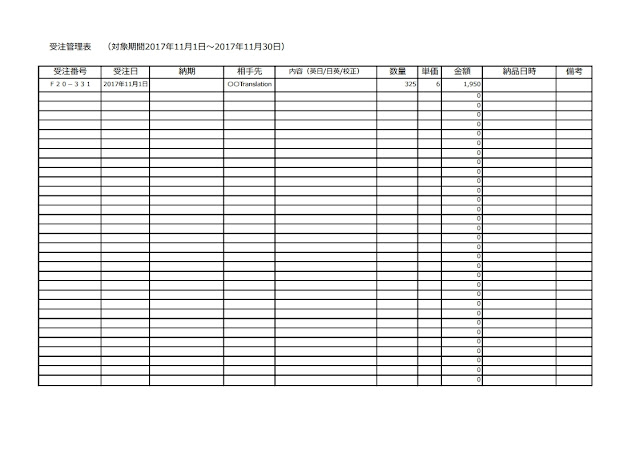個人の翻訳者としての事務仕事については、前半の方で主にお話しさせていただいてきましたが、後半はネタが尽きてしまい、今に至ってしまいました。
でも、年が変わると毎年恒例の確定申告が待っています!!いつも早めにやらねばと思いながら後で切羽詰まってからやるという...子どものころからの習性が抜けていません。
そろそろ領収書の整理など始めなければなりません。
以前にもお話しましたが、私は「マネーフォワード」というオンラインの会計ソフトを使っています。見積書や請求書の作成機能もあるので、普段の仕事の時からバリバリお世話になっています。
このサービスの便利なところは、一旦見積書を作ったらそれを請求書に変換でき、さらには請求書に対して入金処理をすると、自動的に売り上げに反映されるというところです。
最近は他にも類似のサービスも出ているので、これは標準の機能なのかな。
簿記の知識の全くない私でも使えてしまうので、このまま簿記の知識はないままで終わりそうです(笑)。
今年は新規の取引先からも色々とお声をかけていただいたので、確定申告作業はますます煩雑になりそうです。
また何かシェアできそうな情報を得ましたらお伝えします!